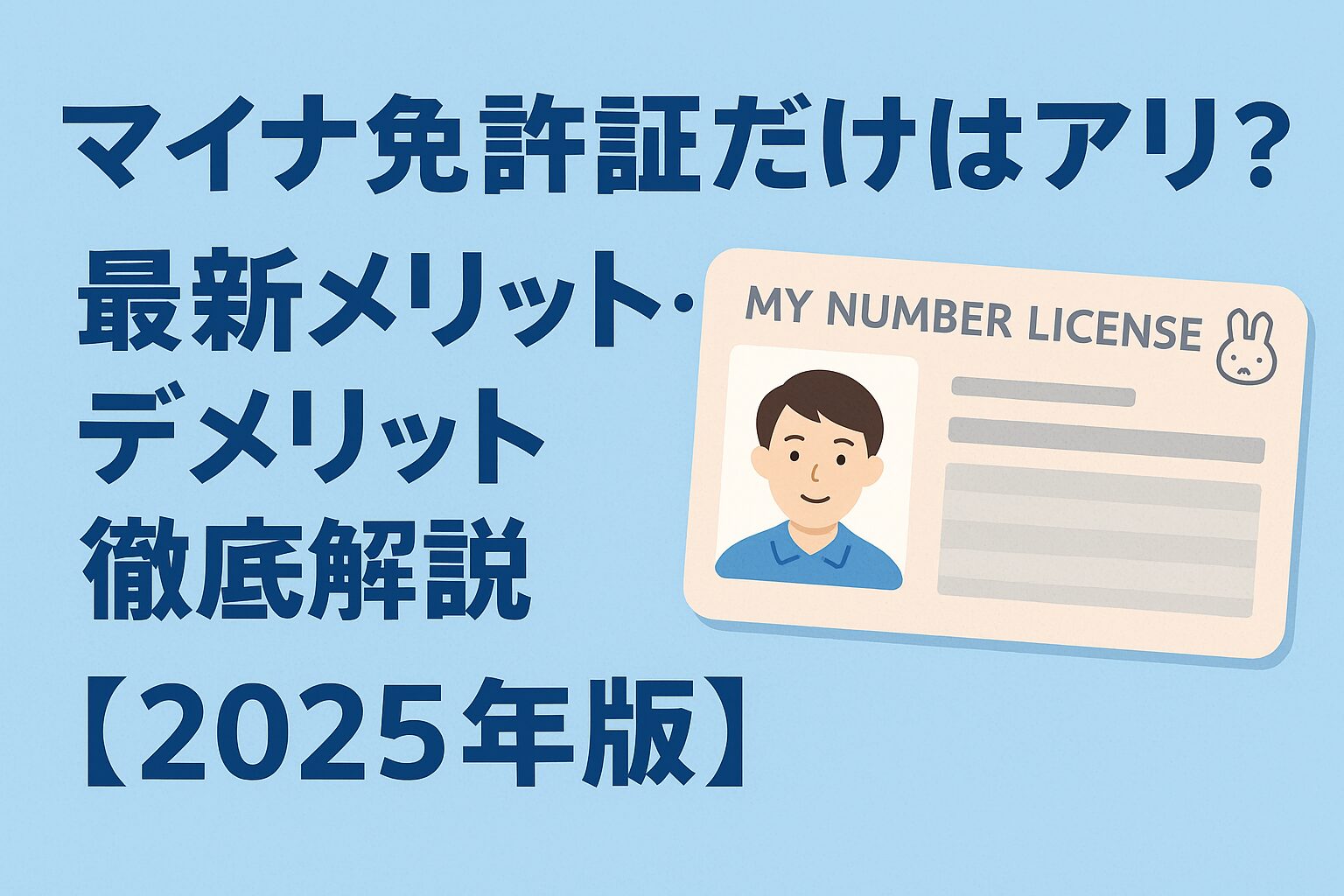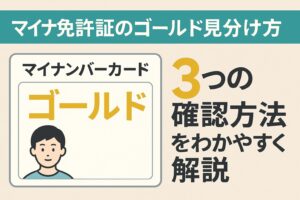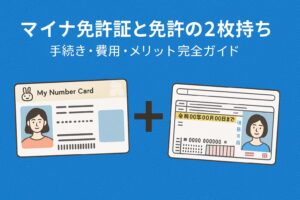2025年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証を一体化させた「マイナ免許証(マイナンバーカードに免許情報を記録)」の制度が全国で開始されました。
これにより、従来の運転免許証と異なる選択肢が生まれ、「マイナ免許証だけ」を持つことを選ぶ人も出てきます。
本記事では、「マイナ免許証だけを保有する」ことにフォーカスし、そのメリット・デメリットを徹底的に解説します。
従来型の運転免許証との比較を交えながら、利用を検討するうえで押さえておきたいポイントを具体的に示します。
マイナ免許証(=運転免許情報を記録したマイナンバーカード)とは何か?
制度の概要と経緯
- 令和4年の道路交通法改正で、マイナンバーカードと運転免許証・運転経歴証明書の一体化に関する規定が整備されました。
- そして、2025年3月24日から全国で運用が始まりました。
- この制度では、従来の運転免許証を保持するか、マイナ免許証と併用するか、マイナ免許証のみ保有するかの3パターンの選択が可能です。
- ただし、義務ではなく、希望者のみが切り替え可能という扱いです。
マイナ免許証における情報の扱い
- 免許情報(免許番号、免許の種類・条件、有効期間など)は、ICチップに記録されます。
- 一方、券面(カードの外観)上には、従来型の運転免許証のような「交付年月日」「公安委員会名」「本籍」などは記載されず、目視での確認はできません。
- 免許情報を確認・読み取るには、マイナ免許証読み取りアプリやマイナポータル(オンライン)を介して行う必要があります。
- また、免許更新時講習をオンラインで受講できるようになる等、制度的な優遇措置も設けられています。I
「マイナ免許証だけ」保有のメリット
以下では、マイナ免許証のみを保有するケースに絞って、「何が得られるか」「どう使えるか」を中心にメリットを整理します。
| 項目 | 内容 | 補足・条件 |
|---|---|---|
| 更新手数料が安くなる | マイナ免許証のみを選ぶと、更新手数料が従来より抑えられるケースがあります。 | 例:従来は 2,850 円だった更新手数料が、マイナ免許証のみなら 2,100 円に |
| 更新時講習をオンラインで受講できる | 講習区分が「優良運転者」「一般運転者」の場合、オンライン講習を事前に受けられ、当日の更新時間を短縮可能となります。 | ただし「違反運転者」「初回更新者」はオンライン講習対象外。 |
| 住所・氏名などの変更手続きがワンストップ化 | 役所で住民票など住所変更等を行えば、警察署で受ける免許記載事項の変更届が不要になる「ワンストップサービス」が利用可能です。 | このサービスを利用するには、署名用電子証明書の提出やマイナポータル連携など事前手続きが必要。 |
| 証明書類を持ち歩く枚数を減らせる | マイナンバーカードに免許情報を含むことで、身分証として使うカード数を削減できます(運転免許証別持ち歩き不要)。 | ただし、免許情報を目視できないため、券面だけでは運転可否や有効期限が確認できない点は注意。 |
| 制度拡張・行政効率化の恩恵 | 一体化制度導入により、行政側の仕組み整備も進む見込み。将来的にはより利便性の高いサービス連携が期待されます。 | とはいえ、初期導入期のため各自治体・警察署の対応状況にばらつきあり。 |
以上が主な利点ですが、実際に「マイナ免許証だけ」を選ぶ際には、制度の制約やリスク・運用上の不便点もよく抑えておく必要があります。
「マイナ免許証だけ」保有のデメリット

マイナ免許証のみを保有することが必ずしも万能とは言えません。以下は主に注意すべきデメリットと事例です。
主なデメリット一覧
以下にひとつずつ掘り下げます。
1. 紛失・破損時のリスクが高まる
マイナ免許証のみ保有している場合、カードを紛失・破損すると、運転できなくなる期間が発生する可能性があります。
- マイナンバーカード自体を紛失・再発行する必要があります。再発行後、新しいカードに免許情報を再記録しなければなりません。
- マイナ免許証だけ保有していた場合、再記録手続きが完了するまで運転できないというケースもあります。
- 再記録・再交付には手数料がかかることもあります。
このように、カード一体化によって“単一障害点”が増える形となります。
2. 目視での免許情報確認ができない
従来の運転免許証は、免許証を見れば有効期限、交付日、公安委員会名などを一瞥できますが、マイナ免許証はICチップ記録方式のため、券面にはそうした情報が記載されません。
- 有効期限を目視で確認できないため、免許更新時期を知らずに失効するリスクが高まります。
- 多くの場面で、提示された免許証の顔写真と有効期限を見て確認する、という慣習が残っていますが、マイナ免許証ではそれができず、カード読み取り機器やアプリが必須となります。
- 特に、警察官・レンタカー会社・交通機関・空港など、目視確認を求められる現場での対応に不安があります。
この「視覚的確認」ができないことは、実務面での抵抗になる可能性があります。
3. 再記録・再交付手続きに時間と手間がかかる
- 紛失・破損の際には、前述のとおり再記録を行わなければなりませんが、それ自体が時間を要する手続きです。
- 特に、警察署・免許センターでの手続き回数が従来より増える可能性があります。
- また、マイナンバーカード更新時期と重なると、カード更新と免許情報記録のタイミングがずれるケースもあり注意が必要です。
4. 利用できない場面・制度との非互換性
マイナ免許証だけという選択には、制度上・実務上で制約が残る場面があります。
- 海外での運転:マイナ免許証は目視での免許証提示ができないため、海外の警察等に無免許扱いされる可能性があります。政府の案内でも、海外運転時には従来型の運転免許証を持参することが推奨されています。
- 免許証抜粋証明の申請:国外在住者向けなどの場合、従来型の運転免許証が必要で、マイナ免許証では受け付けられない場面もあります。
- 警察署・免許更新窓口等の対応状況のばらつき:一部の警察署ではマイナ免許証の手続き自体を行っていないところもあります。大阪府警などでは、すべての署に対応しているわけではなく、免許センターや特定署のみ可、また更新時には2度の来署が必要なケースも。
- 目視確認を前提とした業務・システムとの非互換:たとえばレンタカー会社・警備業・アルコール検査機器など、免許証バーコードや顔写真・記号を目視確認する仕組みが前提の業種では、ICカード読み取り端末の整備が追いつかない可能性があります。実際、制度開始を機にこうした対応が課題となっているという指摘もあります。
5. 暗証番号・電子証明書管理の負荷
マイナ免許証運用には、暗証番号(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書等)管理が必須です。
- マイナ免許証を手続きに使う際、署名用電子証明書の提出や暗証番号入力が求められる場面が多くなります。
- 暗証番号を忘れた場合、本人確認手続きが煩雑になることがあります
- 電子証明書の有効期限も管理する必要があります。
こうした「ICカード+電子認証」の運用負荷を敬遠する人も多いです。
6. 制度開始直後ゆえの運用課題・対応遅れ
マイナ免許証制度は導入直後であり、以下のような初期段階の課題があります。
- 各都道府県警察署や免許センターでの対応準備が整っていない、対応可能時間や受付窓口が限定的であるケース。
- システム障害や読み取り不具合、カード読み取り端末の対応遅延などの技術的トラブル発生可能性。
- 利用者側が新制度・手続き方法に慣れておらず、ミスや混乱が生じる可能性。
- 免許証情報読み取りを前提とした業務側システム改修コスト負担。レンタカー業や交通機関、飲食店・レンタカー業者など、免許証提示を前提とした業務で影響が指摘されています。
これらの課題は、時間の経過とともに改善されていく可能性がありますが、当面は“先行リスク”として念頭に置くべきです。
比較:マイナ免許証のみ vs 従来型免許証のみ vs 両方保有
ここで、「マイナ免許証のみ保有」の状況を、他の2形態と比較しておくと、各選択肢の位置づけが明確になります。
| 保有形態 | 主な利点 | 主な欠点 | 適した人 |
|---|---|---|---|
| マイナ免許証のみ | 更新手数料など割引措置、オンライン講習、手続ワンストップ、カード枚数減少 | 紛失リスク、目視確認不可、再記録手続き負荷、対応未整備の場面あり | 手続きに慣れており、制度の利点を活用したい人 |
| 従来型免許証のみ | 目視確認可、運用実績多数、安心感あり | マイナ制度の優遇措置を受けられない、手続きの重複 | 変化を避けたい保守的な人、制度不安のある人 |
| 両方保有 | 万一マイナ免許証が使えない場面に備えられる | 更新手数料が割高になる場合、管理が煩雑 | 新制度に移行したいがリスクを抑えたい人 |
たとえば、更新手数料に関しては以下の通りです。
- マイナ免許証のみ:2,100 円
- 従来型免許証のみ:2,850 円
- 両方保有:2,950 円
こうした金銭的差異やリスクの兼ね合いを見ながら、自分に最適な選択をすることが重要です。
「マイナ免許証だけ」にするときのチェックリスト・注意点
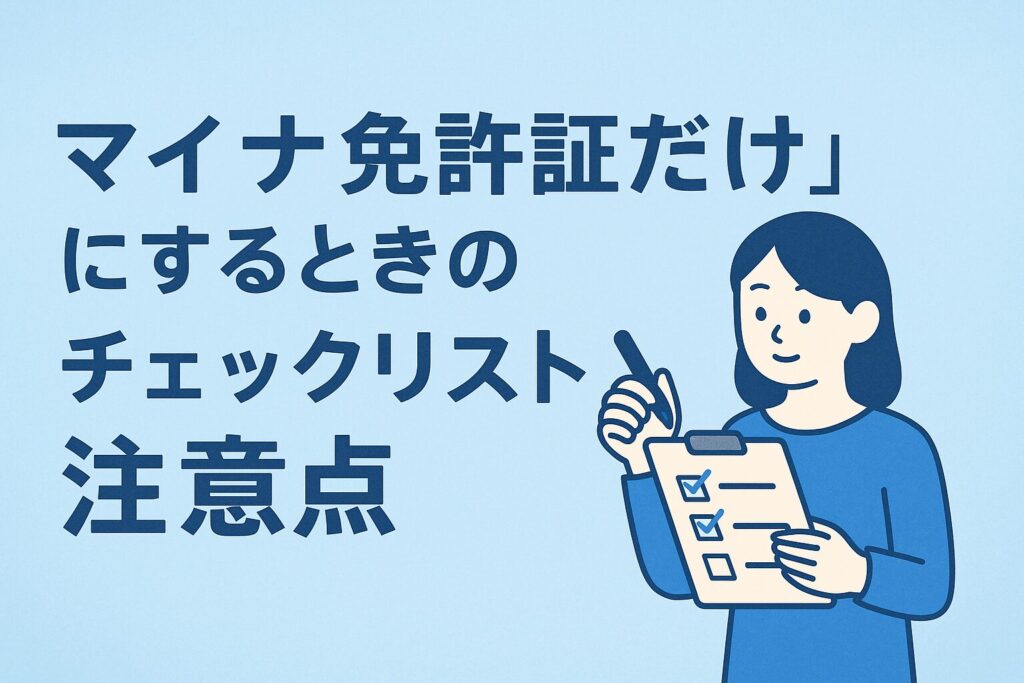
実際にマイナ免許証のみを選ぶ際には、以下の点を事前に確認・準備しておきましょう。
- 免許更新時講習の対象か(「優良運転者」「一般運転者」であるか)
- 署名用電子証明書の登録・提出済みか
- マイナポータルとの連携設定を済ませているか
- 暗証番号を確実に把握・記憶しているか
- 紛失・破損時の再記録手順を理解しているか
- 自分が使うサービス(レンタカー、空港、役所など)がマイナ免許証対応かどうか確認
- 海外で運転する可能性があるなら、従来型免許証を併用する備えも持つ
- 手続可能な場所・受付時間を管轄警察署や免許センターで確認
こうした準備を怠ると、制度を最大限に活かすどころか、リスクを抱えることになりかねません。
まとめ:どちらが「正解」か?
「マイナ免許証だけ保有する」という選択は、制度の利点を最大限享受したい人にとって魅力的な選択肢です。更新手数料の軽減やオンライン講習、手続きの簡便化などメリットは確かに見込めます。
しかし一方で、紛失・破損リスク、目視確認不可という実務上の制約、制度対応の遅れ、暗証番号管理の煩雑さなど、現段階では割引と引き換えにある種のリスクも抱えることになります。
したがって、次のようなスタンスが現実的です。
- 新制度やデジタル化に前向きで、リスク許容度がある人:マイナ免許証のみ保有を検討
- 保守的で安定性を重視する人:従来型免許証のみか、しばらくは両方保有して様子を見る
- 利用頻度・使用先が多様な人(レンタカー利用・海外運転など):当面は両方保有しておくのが安全策
制度導入初期段階では、万全な対応が整っていない地域や事業者もあるため、「周囲の対応状況」を見極めながら移行を検討することをおすすめします。