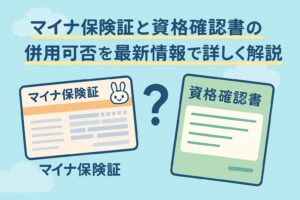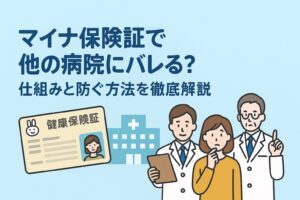マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」が、制度化の流れで注目を集めています。
「マイナ保険証は義務になるのか?」
「いつから義務化?」
「使えない場合はどうすれば?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
本記事では、2025年10月時点での制度の最新状況を整理し、「義務化」の有無、導入スケジュール、そして「資格確認書」との関係も含めて、わかりやすく解説します。
1. マイナ保険証とは
- マイナ保険証は、マイナンバーカードに健康保険証機能を持たせ、医療機関の受付でカードを提示することで保険資格の確認や医療情報の活用ができる仕組みのこと。
- オンライン資格確認システムと連動し、医療機関・薬局でその場で保険資格を確認できるようにするもの。
- 利用には、マイナンバーカードの発行および「保険証利用登録」の手続きが必要。登録していないと使えない。厚労省・デジタル庁もこの仕組みを推進している。
- マイナ保険証を使える医療機関・薬局は、オンライン資格確認に対応している施設に限られる。
2. 義務化という表現の誤解 — マイナ保険証は「義務」ではない!

冒頭で結論を先に述べると、「マイナ保険証の義務化」という言い方は正確ではありません。以下の点を整理します。
| 誤解されやすい表現 | 実際の制度上の立ち位置 |
|---|---|
| 「マイナ保険証が義務化される」 | 現時点では法律で国民にカードを義務付ける規定はない |
| 「健康保険証を使えなくなる」 | 従来の保険証は、有効期限等の条件を満たせば一定期間使える(経過措置) |
| 「カードを持っていなければ受診できない」 | 受診そのものは可能。ただし利用登録していない場合、資格確認書が使われることもある |
つまり、「義務化」という言葉が使われている背景には「従来の健康保険証の新規発行停止」や「カードがない人向けには代替措置(資格確認書)」の存在がありますが、カードを無理に持たせる強制力を持つ制度とは異なります。
3. 移行スケジュールと制度変更の流れ
義務化とは言えないものの、制度として「マイナ保険証を基本とする仕組み」へと段階的に移行が進んでいます。以下の流れを押さえておきましょう。
主な時点と制度
| 日付 | 変更内容・対応 |
|---|---|
| 2024年12月2日 | 従来の健康保険証の新規発行が停止。以降、健康保険証は、保険者が更新する場合を除いて発行されない。 |
| 2024年12月2日~2025年12月1日 | 従来の健康保険証は、資格喪失がない限り有効・使用可能。経過措置として移行期間。 |
| 2025年12月2日以降 | 従来の健康保険証の利用停止(保険証機能として使えなくなる) |
| 2025年7月31日(後期高齢者医療制度) | 後期高齢者医療制度の健康保険証有効期限 → この日以降は新たな健康保険証を発行せず、マイナ保険証への移行。 |
| 2025年9月以降 | 保険者判断で、マイナ保険証を持たない人には資格確認書を交付する動き。 |
このように、「義務化」という表現ではなく、「新規発行停止 → 経過措置 → 完全移行」という流れで制度変更が進んでいます。
なお、制度を運用する上での具体的な手続きや対応スケジュールは、保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市町村国保など)によって若干異なることがあります。
4. 資格確認書とは何か?使われるケース
マイナ保険証を使わない・使えない人向けの代替措置が 資格確認書 です。以下に、制度上の位置づけと具体的な利用例を解説します。
資格確認書の概要と制度
- 資格確認書は、マイナ保険証を利用しない・できない場合に、受診時に保険資格を確認するための書類。医療機関等で提示することで保険診療を受けられる。
- 通常、従来の健康保険証を所持している人には、申請なしに保険者から無償で交付される(ただし保険者によって様式や発行形態が異なる)
- 有効期限は保険者が設定(多くは5年以内)
- 保険者側が「マイナ保険証を持っていない人、マイナンバー登録が未済の人」などの判断をした際、資格確認書を発行する制度設計がある。
- ただし、マイナ保険証を持っているのに資格確認書を発行することは原則認められていない。
資格確認書が使われるケース(例)
- マイナンバーカードをまだ取得していない人
- マイナンバーカードはあるが、保険証利用登録をしていない人
- オンライン資格確認を導入していない医療機関で受診する人
- 保険者が判断して、マイナ保険証を使えないと判断した人
医療機関を窓口で受診するときは、資格確認書を提示すれば、保険診療の自己負担分を支払った上で診療を受けることが可能です。
5. マイナ保険証を使えない・使わない場合はどうするか?
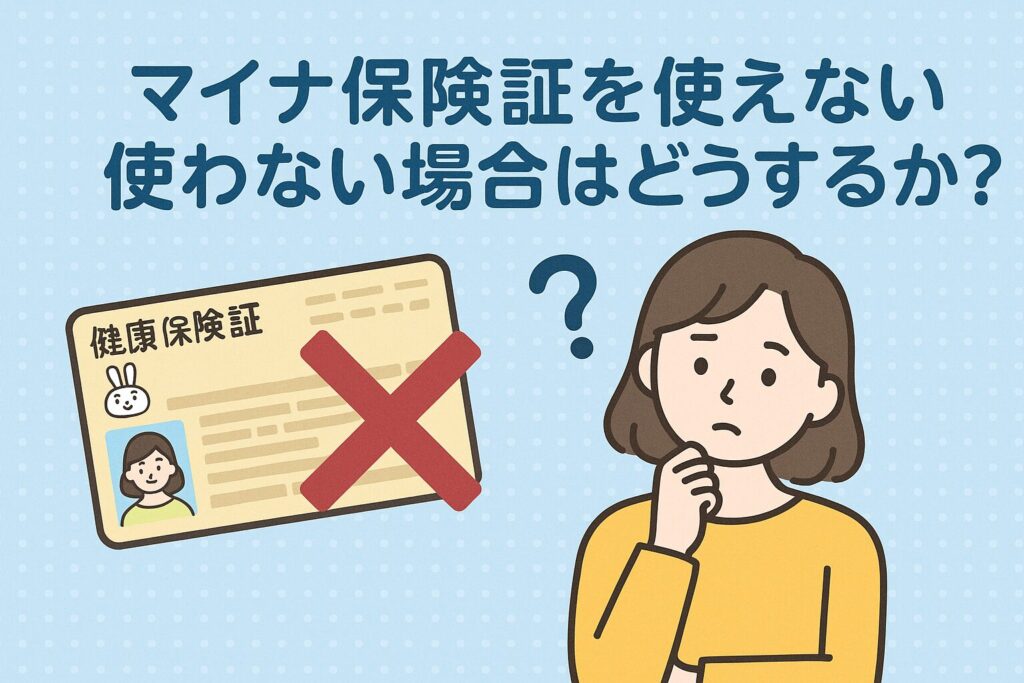
制度変化の中で、「カードを持っていない」「登録していない」「カードを使いたくない」人の扱いはどうなるのでしょうか。以下の対応方法を押さえておきましょう。
受診方法の選択肢
- マイナ保険証を使って受診する
- 登録済みであれば、オンライン資格確認対応の医療機関・薬局でカードを提示すれば、自動的に保険資格が確認される。
- 高額療養費制度での申請手続きが不要となるケースもある(手続き簡略化)
- 資格確認書を使って受診する
- 上記のように、マイナ保険証を使わない/使えない場合の受診手段。
- 有効な資格確認書を窓口に提示して、通常の健康保険診療を受ける。
- ただし、限度額適用認定証等は別途手続きが必要で、メリット(自動適用など)が少ない。
- 実費(保険適用外)での受診(例外的)
- まれなケースとして、保険資格が確認できない場合、全額自己負担での診療になる可能性がある(ただし後日、保険適用分を返還請求できる制度があるケースも)
注意点・留意点
- 医療機関や薬局がオンライン資格確認に対応していないと、マイナ保険証を提示しても旧来の方法で対応される可能性あり。
- 受診日と保険者の登録日のタイミング(反映遅延)によって、資格情報が確認できずに実費扱いになるリスクもある。
- 資格確認書を提示して受診した場合、高額療養費制度の窓口適用・自動適用等の特典が受けられないケースがあるので、別途手続きが必要となる。
- 保険者(国保・組合等)によって制度導入時期・運用が異なることを確認すること。
6. メリット・注意点
マイナ保険証を使うことには利点もありますが、注意すべき点もあります。以下に整理します。
メリット
- 受付業務の効率化・利便性向上:カードをかざせば資格確認が即時でき、受付事務の負担が軽くなる可能性。
- 重複検査の抑制・医療情報の携:過去の検査結果、薬剤情報が医師・薬剤師で共有可能(本人の同意が前提)
- 確定申告・医療費通知の簡素化:マイナポータル経由で医療費通知を取得でき、医療費控除申告の際に活用できる
- 高額療養費制度の取り扱い簡素化:高額療養費制度の手続きが簡略になるケースがある(自動適用など)
注意点・リスク
- 対応医療機関の限定:オンライン資格確認対応の施設でなければ、利用できないことがある。
- システム障害・ネットワーク不具合:システム障害や通信不具合などで資格確認ができないリスク。
- カード・登録未対応者の扱い:カード未取得・登録未実施の人には資格確認書等の対応が必要(自動でカードを取得させるわけではない)
- プライバシー・情報漏洩リスク:医療情報との連携が可能になる分、情報管理・同意・安全性の確保が重要。
- 保険者による運用差:保険者(協会けんぽ・健康保険組合・国保など)ごとに運用ルール・スケジュールが異なり混乱が起きる可能性あり。
7. Q&A形式で、よくある疑問に回答
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| マイナ保険証は法律で国民に義務付けられるの? | いいえ。現時点では義務付ける法律はない。「義務化」という言葉は、従来保険証の発行停止やカード前提の制度設計を指して使われることが多い。 |
| 従来の健康保険証は完全に使えなくなる? | 既発行済みの健康保険証は、有効期限内かつ資格喪失がなければ、2025年12月1日まで使用可能(経過措置) |
| 2025年12月2日以降はどうなる? | 従来の保険証は保険証機能として使用停止となり、マイナ保険証または資格確認書等で受診対応となる。 |
| まだマイナンバーカードを持っていない場合は? | まずカードを申請・取得し、次に保険証利用登録をする必要がある。受診時には資格確認書等で代替対応となる。 |
| 医療機関がオンライン資格確認に対応していないときは? | 従来の診療受付方式(紙の保険証や資格確認書提示など)で対応する可能性がある。 |
| 資格確認書の交付を申請する必要がある? | 通常、保険者から自動的に交付される(申請不要)。ただし方式・タイミングは保険者による。 |
| 資格確認書に有効期限はある? | はい。保険者が定める期限(多くは5年以内など)あり。 |
| マイナ保険証を使った方が得? | 利便性、情報連携、高額療養費制度の簡略化などの面でメリットがあるが、対応医療機関や情報管理体制などの注意も必要。 |
8. まとめ・今後の展望
- 「義務化」という表現は正確ではないが、制度は確実にカード前提へ移行中。2024年12月2日以降、従来保険証の新規発行は停止され、最終的には2025年12月2日に従来方式は使えなくなる。
- スムーズな受診・保険利用を望むなら、マイナンバーカード取得および保険証利用登録を早めに行うのが得策。
- 資格確認書はあくまで代替措置。カード利用が前提とされる場面が増えるため、長期的にはカード活用が主流になる見込み。
- 今後、医療機関・薬局のオンライン資格確認導入率拡大、制度案内の徹底、システム安定性の確保が鍵となる。
本記事が「マイナ保険証 はいつから義務化 ?」に関する疑問解消に役立てば幸いです。