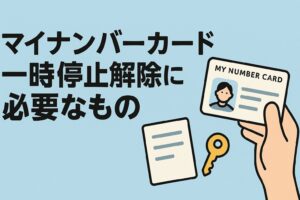マイナンバーカードをなくしたり、破損して使えなくなったとき、いざ再発行しようとしても「何を準備すればいいのか分からない」と迷う方は多いでしょう。
この記事では、マイナンバーカードの再発行に必要なものをわかりやすく整理し、申請の流れや注意点までを最新情報(2025年10月時点)で詳しく解説します。
これを読めば、再発行手続きをスムーズに進められます。
再発行(再交付)が必要となる主な理由は?
マイナンバーカード(個人番号カード) の紛失・破損・機能停止・追記欄満欄などの理由により、新しいカードを交付する手続きが「再交付」です。
「再発行」と呼ばれることもありますが、ここでは「再交付」と同義として扱います。
再交付が必要となる主な理由
- 紛失・盗難・焼失・著しい損傷などカードが使用できなくなった場合。
- 氏名・住所・記載事項の変更があり、追記欄が満欄になってしまった場合。
- 有効期限切れ・国外転出・在留資格変更など特別な事情でカードが失効・使えなくなった場合。
このようなケースでは、手続き・準備すべき「必要なもの」が自治体ごとに定められていますが、共通項も多くあります。以下で、2025年10月時点での“必要なもの”を整理し、表形式でまとめ、その後に「どのように手続きするか」「よくある疑問」なども解説します。
再交付申請に必要なもの一覧📌
以下の表は、一般的に必要となる「準備物・書類・手続き手順・手数料」などを整理したものです。お住まいの市区町村によって細部(例えば手数料の額・窓口受付時間など)は異なりますので、申請前に必ず自治体の公式ウェブサイトで確認してください。
| 項目 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 本人確認書類 | 運転免許証・パスポート・顔写真付き在留カードなど<1点>、または保険証・年金手帳など<2点> | 顔写真付きであれば1点で済むケースが多いです。 |
| 顔写真(最近6か月以内撮影) | 縦4.5cm×横3.5cm、無帽・背景無地・正面向き | 紛失・再交付ではこの写真が必要な自治体が多い。 |
| 旧マイナンバーカード(持っている場合) | 紛失・焼失では持っていないケースが多いですが、損傷・記載追記満欄などの理由では提示が求められます。 | |
| 紛失・盗難・焼失の証明書類 | 外出先で紛失 → 警察の「遺失届/盗難届」の受理番号が必要。焼失 → 消防署等のり災証明書。 | |
| 申請書/申請受付 | 各市区町村窓口で「再交付申請書」を取得・記入。オンライン対応エリアも増加中。 | |
| 手数料 | 再交付には手数料がかかるのが原則。例えば「800円+電子証明書200円」など。特急発行の場合は料金アップ。 | |
| カード受取り時の本人来庁 | 新しいカード交付時には本人が窓口に来る必要がある自治体が多数。代理人不可・制限あり。 | |
| 旧カード機能停止の手続き | 紛失・盗難では、まずカード機能の「一時停止」手続き(無料)を行うことが強く推奨されています。 |
どのように手続きを進めるか?
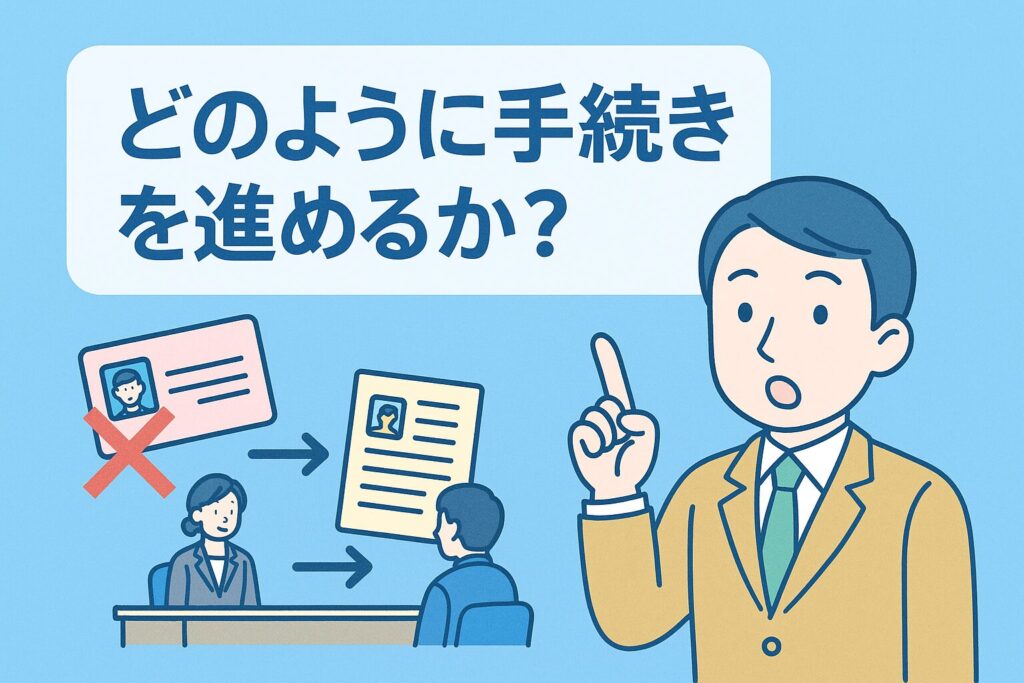
再交付をスムーズに行うため、手続きの流れを「何を・どこで・どの順番で」行うか明確にしておきましょう。
① 紛失・盗難・破損を確認・報告
- カードを紛失または盗難された場合、まずは機能停止の申し出を行いましょう。窓口・24時間対応のフリーダイヤルがあります。
- 外出先で紛失・盗難の場合、警察署・交番へ「遺失届・盗難届」を提出し、受理番号を控えておきます。
- 焼失や著しい損傷の場合、消防署等で「罹災証明書」を取得しておくと手続きがスムーズです。
この段階で「カード自体がどうなったか(無くした・破損した・漏えいの可能性)」を整理しておくと、後の申請時に混乱が少なくなります。
② 再交付申請書の取得・記入
- 市区町村の窓口や公式ウェブサイトから「個人番号カード再交付申請書」を入手します。紛失の場合は「紛失・廃止届」の別書式が必要な自治体もあります。
- 必要事項(氏名・住所・理由等)を記入し、顔写真・本人確認書類・受理番号等を添付・提示します。
- 申請区分(通常/特急)を確認して、手数料を支払うタイミングを把握しておきましょう。特急発行の場合、費用が高め・窓口対応のみの場合があります。
③ 新カードの交付・受取り
- 申請が受理されると、自治体から交付準備完了の通知(ハガキ等)が届きます。
- 指定日時・窓口でカードを受け取る際、本人確認書類の提示・暗証番号設定が必要です。代理人受取り不可のケースも多いため注意。
- 受取完了後、旧カード(所持していた場合)は返納・破棄手続きを行います。
④ 紛失後のフォロー
- 新しいカードを受け取るまでは、住民票や通知カード(既に交付済の場合)などによってマイナンバーの証明が必要になる場面があります。
- また、カードを紛失した原因・対応(例えば、外出時に落とした・自宅内で見当たらない等)を整理しておくことで、今後の防止策につながります。
- 万が一、番号漏えいのおそれがあると自治体が判断した場合、マイナンバー(12桁の個人番号)の変更請求手続きが可能です。
よくある疑問・Q&A形式で解決
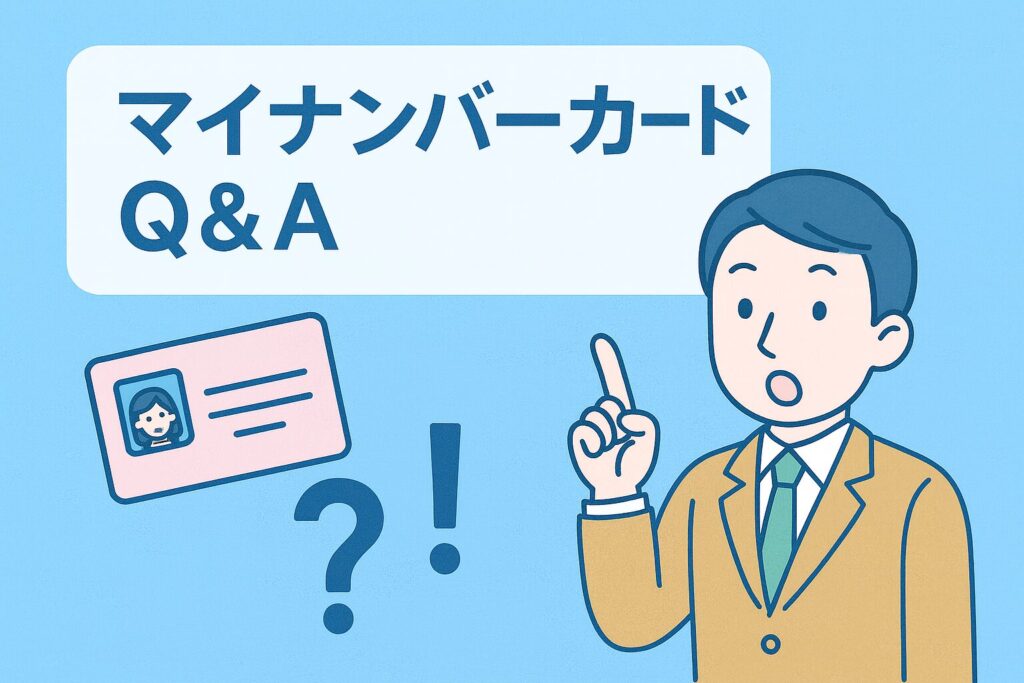
Q1. 再交付の手数料はいくら?
A. 多くの自治体で、通常再交付手数料は 800円 としている例が見られます。電子証明書の搭載を希望する場合はプラス200円がかかることが一般的です。
ただし「特急発行」の場合は1,800円〜2,000円程度かかる自治体もあります。
※自治体により異なるため、申請前に金額を確認してください。
Q2. いつまでに申請すればいい?
A. 紛失・盗難の場合、速やかに機能停止を行い、30日以内に申請が望ましいという案内もあります。
ただし、30日を過ぎてしまっても多くの自治体では相談を受け付けていますので、焦らず最寄りの窓口へ連絡してください。
Q3. どんな理由でも再交付は無料ではないの?
A. いいえ、無償になるケースもあります。例えば、氏名・住所変更など「本人の責任でない」理由(転居・転出生等)で「追記欄満欄」になった場合など、手数料無料の事例があります。
しかし、紛失・盗難・破損など「本人の管理責任がある」状況では手数料が発生するのが通常です。
Q4. 代理人でも再交付申請できる?
A. 基本的には本人の申請・本人の受取りが必要という自治体が多いです。代理人申請・受取りには別途「委任状」「法定代理人証明」などが必要となります。
未成年・成年被後見人の場合は、法定代理人が申請・受取を行う場合があります。
Q5. 再交付中、マイナンバーの証明が必要な場合は?
A. カードを再交付中にマイナンバーを証明する必要が生じたときは、「マイナンバー入り住民票の写し」を取得する方法があります。
また、自治体ごとに「仮交付証明」などの対応がある可能性もありますので、申請窓口で確認ください。
再交付にあたってのポイントと注意点💡
- カードの機能停止を早めに:紛失・盗難の場合、カードのICチップ内には電子証明書等の機能があるため、早期に停止手続きを行うことで不正利用のリスクを減らせます。
- 顔写真の準備忘れに注意:顔写真サイズ・無帽背景・最近撮影という規定が厳格です。証明写真データでこの条件を満たしていないと再提出を求められる場合があります。
- 旧カードを持っている場合でも回収対象:再交付の理由が「追記欄満欄」「損傷」などの場合、旧カードを窓口で返納する必要がある自治体があります。
- 時間に余裕を持つこと:通常は申請後1〜2か月かかるケースもあります。特急申請を使えば1週間程度で交付される例もありますが、条件・費用が異なります。
- 番号変更は例外的:通常、マイナンバー(12桁)は再交付しても変わりません。番号変更は「番号が漏えいした恐れがある」「不正使用が認められる」等、特別な事情がある場合のみ可能です。
2025年10月時点で覚えておくべき最新の動き🔍
- デジタル庁は、紛失・盗難などによる再交付で「特急発行・交付制度」を紹介しており、申請から原則1週間でカードが届く可能性があることを明示しています。
- 各自治体の手続き・手数料・申請窓口の体制も刷新されつつあり、オンライン申請・予約制度を導入しているところも増えてきています。
- マイナンバーカードの利活用(保険証利用・デジタル証明など)が拡大する中で、カード自体を「身分証明書+IC機能付き本人証明」として重要性が高まっており、再発行・再交付の際の「必要なもの」を事前準備しておくことがますます重要です。
まとめ:何を準備して、どう動けばいいか?
「マイナンバーカード再発行に必要なもの」
- まずカードを紛失・破損した場合は機能停止と届出を
→ 24時間受付のフリーダイヤル・警察署等での遺失届など - 再交付申請書を取得し、本人確認書類・写真・証明類を揃えて窓口へ
→ 顔写真・本人確認・受理番号など - 手数料を確認し、申請・交付を行う
→ 通常800円+電子証明書等200円、特急の場合は更に加算 - カードを受け取ったら、旧カードがあれば返納・暗証番号設定を確実に
- 万が一、番号漏えいの恐れがある状況なら番号変更も検討
以上を押さえれば、「何を?」「どのように?」準備すればいいかがクリアになります。
お住まいの市区町村が定める細かい手続き・窓口時間・費用などは、その自治体の公式情報を必ず確認してください。