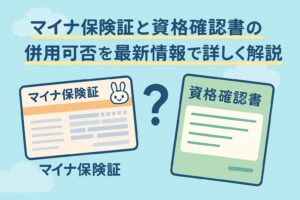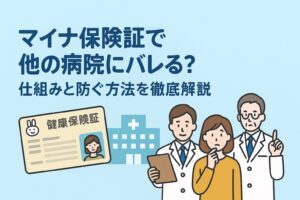マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」制度は、医療DXの基盤となる重要な取り組みです。
しかし実際には、利用登録を解除したいという声も一定数あります。
「なぜ解除したいのか?」
「解除するとどうなるのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、「マイナ保険証なぜ解除申請するの?」をキーワードに、解除希望の背景から手続き手順、注意点まで、最新の情報をもとに整理して解説します。
1. マイナ保険証(健康保険証利用登録制度)の概要
まず前提として、マイナ保険証制度の仕組みと現状を簡単に整理します。
制度の目的と仕組み
- マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の機能を付与し、医療機関や薬局でカードを提示すれば オンライン資格確認 を行える仕組みです。
- 医療履歴の参照、重複投薬防止、電子化の促進など、医療DXや安全性向上を目的としています。
- 2024年12月2日以降、従来の健康保険証については新規発行・再交付が終了され、マイナ保険証を基本とする運用に移行中です。
- ただし、移行措置として、従来の保険証を 2025年12月1日まで有効 とする経過措置が設けられています。
登録・利用開始
- 利用登録を行うと、医療機関・薬局でマイナンバーカードをそのまま提示して受診・調剤が可能です。
- 登録にはマイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きリーダーなどから操作が可能です。
以上が前提です。この制度に「解除申請」が認められるようになった背景と理由を以下で見ていきましょう。
2. 解除申請(利用登録解除)とは何か
「解除申請」とは、すでにマイナンバーカードに健康保険証の機能を登録している者が、その登録を取り消す(無効化する)手続きを指します。公式には「マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除する(利用登録解除)」と呼ばれます。
解除申請が認められたのはいつからか
もともとマイナ保険証への利用登録は「任意」とされていましたが、登録後の解除は原則できない運用とされていました。しかし、2023年に政府は、利用登録自体が任意であることを踏まえ、「登録後でも解除を認める方針」を示しました。
その後、2024年10月に厚生労働省は「マイナ保険証の利用登録解除の運用について」という通知を発出し、各保険者に加入者からの解除申請の受付を開始するよう指示しました。
つまり、2024年10月28日あたりから、保険者側で登録解除申請を受付ける体制が整備され始めたという流れです。
解除申請の効果・制限
- 解除されると、マイナンバーカードを健康保険証として使えなくなります(オンライン資格確認は無効)
- 解除後は、医療機関・薬局では 資格確認書 の提示が求められます。
- 解除の反映には一定の時間(1〜2か月程度)がかかります。
- ただし、従来型の保険証(青いカード・紙の保険証等)を有効なものとして持っていれば、それを使い続ける形になります。
この解除申請制度を導入した背景には、利用者側の不安・使い勝手の課題があるためです。次にその理由を深掘りします。
3. なぜ人は解除を希望するのか?背景と理由
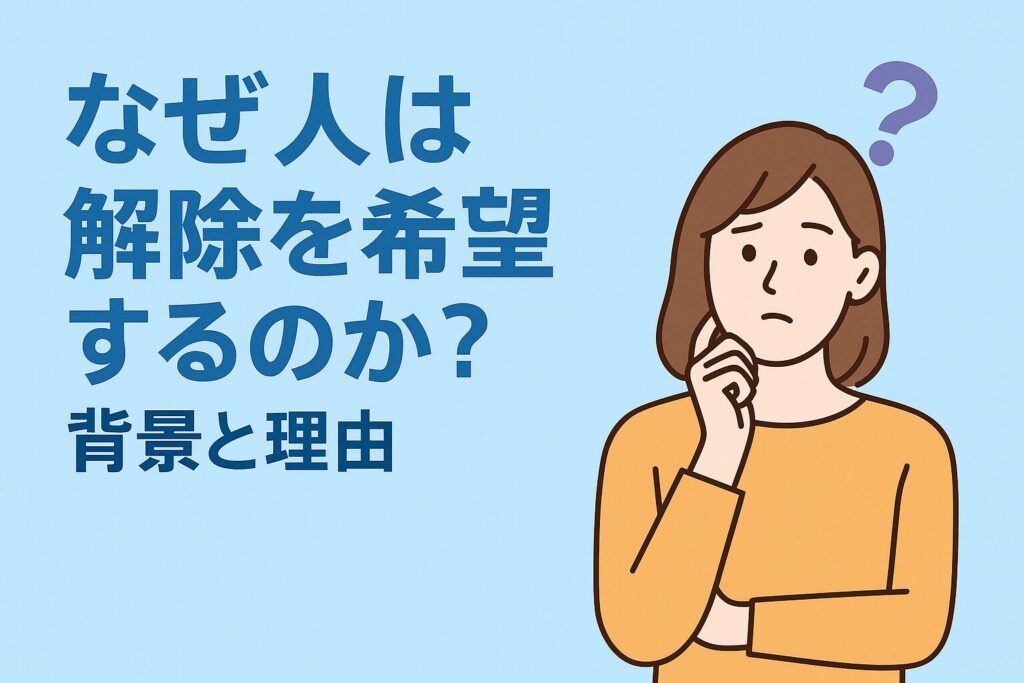
実際に「マイナ保険証 解除申請」を行う人が増えてきており、報道やアンケートから、主な理由や心理が見えてきています。
主な解除理由
以下は、報道・コラム・自治体情報等から抽出されたいくつかの解除理由です:
| 理由 | 内容・背景 | 備考 |
|---|---|---|
| 利便性を感じない | 医療機関・薬局が対応していない、カードリーダーの不具合・エラーがあるなど、使い勝手が悪い | |
| トラブル発生 | 保険資格の照合ミス、被保険者番号・氏名等の誤登録、認証失敗など | |
| セキュリティ・プライバシー懸念 | カード提示で診療履歴や医療情報が参照されることへの不安 | |
| カードを持ち歩きたくない | 利用時にカードを持参しなければならない点が煩わしい | |
| 資格確認書を希望 | 従来の資格確認書で安心したい、現物書類で提示したい |
たとえば、ある自治体では解除申請数が急増しており、品川区では「カードを持ち歩きたくない」が最も多い理由だったとの報道もあります。
また、3か月で5.8万人以上が解除申請を行ったとの報道もあります。
このように、システムの未整備や使い勝手・安心感の欠如が、解除希望の主な背景といえます。
4. 解除申請の条件・受付開始時期
解除申請を受け付けるためには、制度上の条件および受付開始のタイミングがあります。
申請できる人
- すでに マイナンバーカードに健康保険証利用登録をしている方 が対象です。
- 国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合、後期高齢者医療制度など、加入している保険者が受け付けていれば申請可能です。
- 代理申請も可能ですが、委任状や代理人の本人確認書類が必要です。
ただし、保険者によっては、受付を開始していない自治体・組織もあるため、必ず加入している保険者・自治体の案内を確認する必要があります。
受付開始時期・制度変更
- 2024年10月から、保険者側で解除申請の受付を可能とする運用通知が開始されました。
- 実際に多くの自治体が2025年春〜夏ごろから申請受付を開始しています。たとえば、浜松市では解除申請を窓口・オンラインで受け付け。
- 保険者(健保組合・協会けんぽ等)においても、申請受付を案内する動きが広がっています。
- 解除申請の反映は、申請から 1〜2か月程度 要するケースが多く、2か月以上経過しても解除されない場合は、保険者に問い合わせを行う旨の注意も公式FAQにあります。
例えば、神戸市の案内では、受付後解除登録を順次行い、通常1〜2か月で利用解除されると記載されています。
5. 解除手続きの方法(申請先/必要書類/窓口・郵送・オンライン可否)
解除申請を行う際の具体的な手順を、できるだけ汎用的な形と、代表的な保険者・自治体の例を交えて説明します。
申請先(提出先)
解除申請先は、あなたが加入している 保険者(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険を扱う自治体など) です。
たとえば、
- 国民健康保険加入者 → 市区町村の国保担当窓口(保険年金課など)
- 健康保険組合加入者 → 所属の健保組合(加入先組合の健康保険担当窓口)
- 協会けんぽ加入者 → 協会けんぽ支部や加入者が所属する支部など
自治体サイトには、「受付窓口」案内が掲載されていることが多いです(例:浜松市、横浜市など)
必要書類・提出書類
一般的に提出を求められる書類は次のとおりです:
| 提出書類 | 詳細・補足 |
|---|---|
| マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書 | 保険者所定の様式(PDF等) |
| 本人確認書類 | 顔写真付きの公的証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)1点、または写真なし書類2点での確認 |
| 保険者識別情報 | 被保険者証、被保険者番号、保険者名など記載されたもの(記号番号など) |
| 代理申請の場合 | 委任状、代理人の本人確認書類、代理権を示す書類などが必要 |
提出書類や本人確認の基準は保険者・自治体ごとに若干異なりますので、申請前に提出先の案内を確認してください。
提出方法(窓口/郵送/オンライン)
多くの自治体・保険者は次のような方法を提供しています:
- 窓口申請:最も利用されやすい方法です。市区町村役場、健康保険組合事務所などに直接窓口で書類を提出。
- 郵送申請:書類を郵送で提出できる自治体もあります。コピーや封筒の指定、簡易書留・特定記録推奨のケースもあります。
- オンライン申請:現時点ではマイナポータルからの解除申請はできない旨、FAQで案内されています。
- ただし、マイナポータルで申込状況の確認などは可能です。
- また、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMなどから利用登録(再登録)は可能ですが、解除は保険者手続きとなります。
たとえば、横浜市では申請書・本人確認書類を保険年金課窓口に提出する方法を案内しており、郵送申請も可としています。
浜松市も窓口・オンライン申請の案内を出しています。
申請後の処理・反映
- 解除申請を受理してから、登録解除処理が完了するまで通常 1〜2か月程度 かかります。
- もし 2か月以上経過しても解除されない 場合、保険者に問い合わせるよう案内があります。
- 解除が反映されたかどうかは、マイナポータルで「健康保険証利用登録の申込状況」画面から確認できます。
- また、解除申請中に保険者変更が発生した場合(転職・転居等)、新しい保険者に対して「以前の保険者で解除申請を行った」旨を申し出る必要があります。
6. 解除後・申請中の扱い:保険診療・資格確認書など
解除申請・解除後に、以下のような影響や注意点があります。
医療機関での受診・保険診療
- 解除申請中でも保険者資格は変わらないため、保険診療としての自己負担割合が変わるわけではありません。マイナ保険証を使っていないだけで、保険診療は受けられます。
- ただし、医療機関・薬局ではマイナ保険証によるオンライン確認ができないため、資格確認書の提示や従来の保険証提示が必要となります。
- もし従来の健康保険証を持っていない場合、保険者から 資格確認書(書面) が交付され、それを医療機関等に提示する形になります。
資格確認書(保険証代替書類)
- 資格確認書とは、マイナ保険証以外の形で保険資格を証明する書面で、保険診療を受ける際に医療機関・薬局で提示します。
- 保険者によって書式や交付形態は異なります。
- 交付は、解除申請者に対して保険者が行います。
- ただし、従来型の健康保険証を保持している場合、その保険証を使い続けられるケースもあり、資格確認書が交付されない自治体もあります。例えば、神戸市では、有効な従来の保険証を持っている場合は資格確認書を交付しないとの案内があります。
- 資格確認書の交付は、2025年7月以降、協会けんぽが保有者に順次送付を開始する動きも報じられています。
従来型保険証との関係(併用・経過措置)
- 従来型保険証(青いカード等)を持っている場合、有効期限内であれば解除後もその保険証を使えるケースがあります(自治体・保険者の運用により異なる)。
- ただし、従来型保険証は 2025年12月1日まで が有効期限とされ、その後は使えなくなる見込みがあります。
- そのため、解除を行っても、将来的にはマイナ保険証または資格確認書の使用に切り替える必要性があります。
7. 再登録・登録の復活は可能か
マイナ保険証の利用登録を解除した後でも、再度登録することは可能 です。
再登録の方法は、初回登録と同様にマイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーなどを通じて行えます。
ただし、保険者間での異動(転職・転居など)があった場合は、新しい保険者のルールにも従う必要があります。
8. よくある質問とトラブル事例
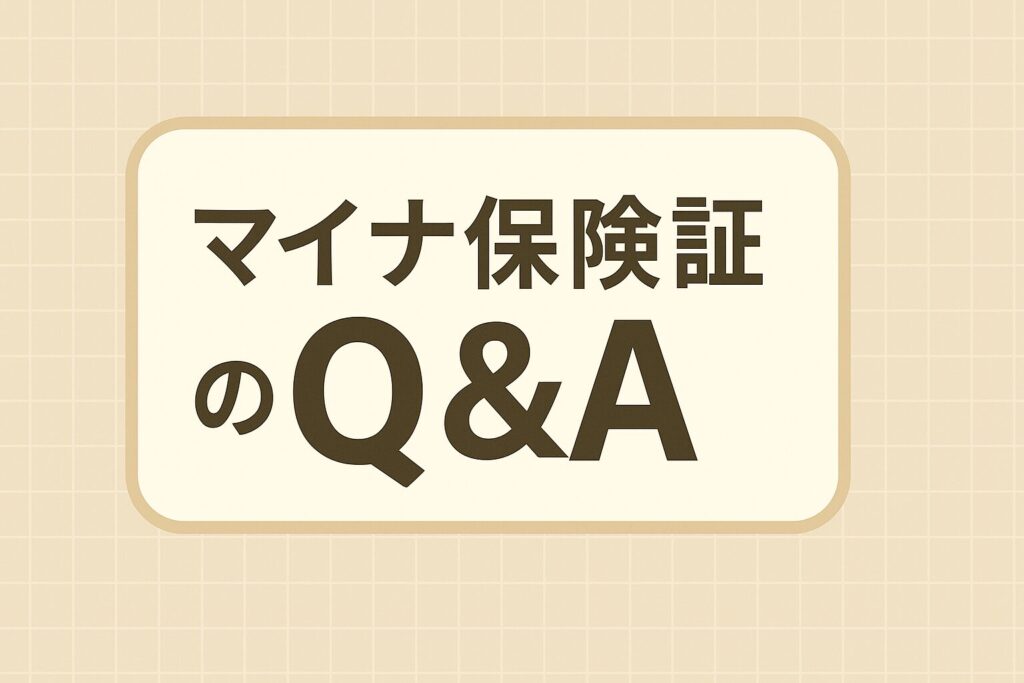
以下、読者が抱きやすい疑問や実際に報じられたトラブル事例をQ&A形式で整理します。
Q1. 解除申請中でも保険診療は受けられますか?
A. はい。解除中でも、保険者資格は変わらないため保険診療は受けられます。ただし、医療機関・薬局側でマイナ保険証が使えないため、資格確認書や従来型保険証の提示が必要です。
Q2. 解除してもペナルティはありますか?
A. 制度上、解除に対するペナルティは特に設けられていません。再登録も可能です。
Q3. 申請してから解除までどれくらいかかる?
A. 通常は 1〜2か月程度 ですが、保険者によっては処理が遅れることもあります。2か月以上経っても処理されていない場合、保険者に問い合わせを。
Q4. すでに医療機関でマイナ保険証を提示していたが、受付できなかった
A. カードリーダーの故障、認証エラー、保険情報の登録ミスなどが原因として報告されています。こうしたトラブルを理由に解除を望む人もいます。
Q5. 保険者が解除を受け付けていない自治体ではどうなる?
A. 制度開始直後は保険者によって対応状況にばらつきがあります。申請を受け付けていない保険者では解除できないため、保険者・自治体の案内に従うしかありません。
Q6. 解除しても再度解除前の医療履歴が参照される?
A. マイナ保険証を使わないだけで、過去の医療履歴そのものが消えるわけではありません。ただし、利用登録解除後は医療機関側で電子的な参照を行う仕組みが一時使えなくなることがあります。
Q7. 解除申請をしたら従来型保険証しか持ってないと困る?
A. 保険者によっては、従来型保険証を保持していない人向けに資格確認書を交付する運用をしています。ただし、交付タイミングや運用方法は異なりますので事前確認が必要です。
9. まとめ:解除を考える前に押さえておきたいポイント
最後に、マイナ保険証解除を検討する際に意識しておきたい要点をまとめます。
- 解除には合理的な理由がある:利用者からの不満・不具合・プライバシー懸念など、解除希望は一定理解できる背景があります。
- 事前確認が不可欠:所属する保険者・自治体が解除申請に対応しているか、提出書類や受付窓口等を公式サイトで確認しましょう
- 解除は即時ではない:1~2か月程度かかるため、その間の受診手段(資格確認書など)を用意しておきましょう。
- 従来保険証との併用に注意:解除後も従来型保険証が使えるケースがありますが、有効期限や制度変更に注意が必要です。
- 将来的な逆登録も可能:解除後でも再登録はできますが、保険者変更等がある場合はその対応も考慮が必要です。
- 登録解除しても医療アクセスには支障がないが手間は増える可能性:医療現場での利便性や認証の安定性を見て判断することが重要です。
解除申請は制度上可能になりましたが、「解除すれば安心・快適」とは必ずしも言えません。メリット・デメリットをよく比較し、申請するかどうかを判断されることをおすすめします。