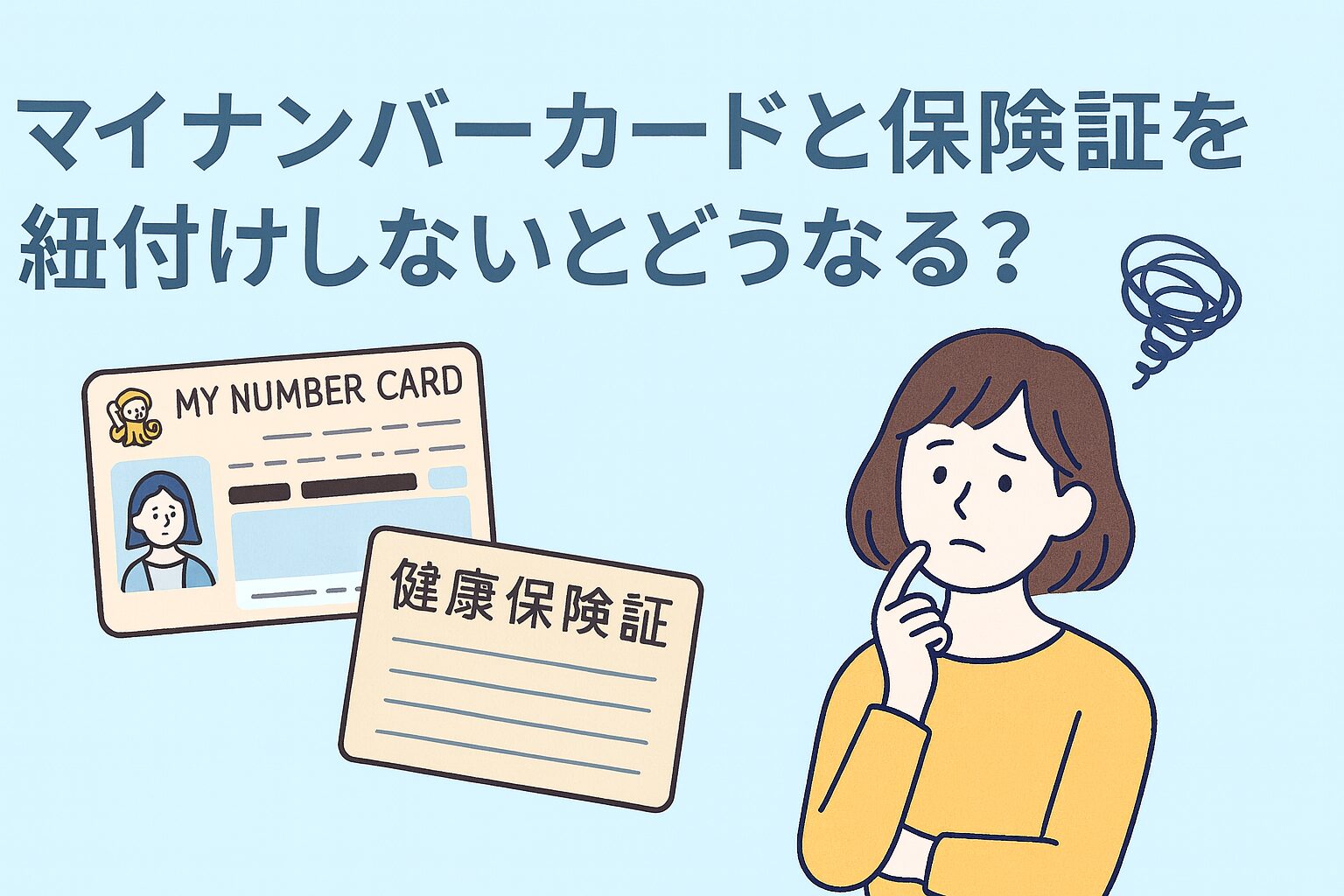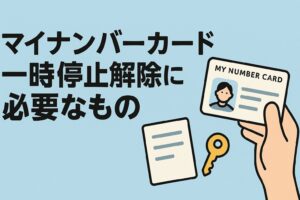マイナンバーカードを健康保険証として利用する“紐付け”の手続きをしていないとどうなるか?
不安を抱えていることでしょう。
この記事では、2025年10月時点の制度最新情報をもとに、手続きをしない場合の影響や安心して受診できるためのポイントをわかりやすくご説明します。
「マイナンバーカードと保険証の紐付け」とは?
制度の概要
「マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録(=紐付け)」とは、マイナンバーカードに加入している健康保険の資格情報を連携させ、医療機関や薬局でカードを提示して保険診療を受けられるようにする仕組みです。
この登録を行ったカードは「マイナ保険証(通称)」と呼ばれます。
なぜ今、紐付けが進んでいるのか?
医療保険証の発行形態が変わるためです。例えば、2024年12月2日から、従来の健康保険証の“新規発行”が停止され、以降はマイナンバーカードを活用する仕組みに移行中です。
このため、「紐付けしていないとどうなるか?」という疑問が増えています。
紐付けをしないとどうなる?影響とリスクを整理🚨
紐付けをしなかった場合、どんな影響が出るのかを「手続き・受診・安心の観点」から整理します。
| 項目 | 紐付けしていない場合の状況 |
|---|---|
| 健康保険証の新規発行 | 2024年12月2日以降、従来の保険証の“新規発行”が停止。紐付けしていないと新たな保険証入手手続きがスムーズでない可能性があります。 |
| 医療機関・薬局での受診 | 紐付けなしでも受診自体は可能ですが、「資格確認書」という代替書類が必要になるケースがあります。 |
| 高額療養費制度などの自動適用 | 「紐付け+データ提供に同意」していない場合、制度利用手続きで従来どおり手間がかかる可能性があります。 |
| 手続きの煩雑さや時間的ロス | 転職・保険者変更・引越しなどで保険者が変わった際、紐付け済みならカードで即利用可能ですが、紐付けなしだと保険者からの「資格確認書」の交付待ちになるケースがあります。 |
結論:大きなペナルティはないが“手間や不安”が増える
現時点では、紐付けしていなければ「保険診療を一切受けられなくなる」というわけではありません。制度として「紐付けしていない方には資格確認書が交付される」仕組みが整えられています。
ただし、必要な手続き・受診時のスムーズさ・将来の保険証制度への備えという観点から、「紐付けしておく」ことが安心につながります。
「紐付けしない場合に起きること」3つのケース🔔

読者の方が具体的に想定しやすいよう、パターン別に「紐付けしないとどうなるか」を解説します。
ケース1📌:転職して保険者が変わった時
転職・退職・会社変更などで加入保険者が変わると、従来は新しい保険証が発行されていました。
しかし紐付けしていない場合、以下のようなことが起こり得ます:
- 新加入の保険者から従来の保険証が発行されず、「資格確認書」が交付される。
- 医療機関・薬局で「カードの提示」「資格確認書の提示」など、受付時に手続きが増える可能性。
- カードに切り替えていれば保険者変更後もマイナンバーカードをそのまま使えたというメリットを活かせない。
ケース2📌:保険証の有効期限が切れた、または保険者変更なしでも更新が必要な時
保険証には有効期限がある場合があります。
紐付けしていないと:
- 従来の保険証の有効期限を過ぎると、次の保険証が発行されない場合がある。
- 医療機関で「保険証が有効ではない」と判断される可能性があるため、事前に保険者に確認する必要。
- 紐付け済みなら保険者変更・更新手続き後にマイナンバーカードをそのまま使えるという手軽さが失われる。
ケース3📌:受診時・薬局利用時にスムーズに進めたい時
病気・ケガで急に受診する際、「カードを持っていない」「紐付け手続きが未完了」「資格確認書提示が必要」という状態だと:
- 受付時に通常より時間がかかる可能性がある(本人確認・資格確認の手続きが増える)。
- 医療機関・薬局によっては「マイナ保険証に未対応」の場合もあり、別の保険証や資格確認書が必要になることがある。
- 手続きをあらかじめ済ませておけば「窓口でのスムーズ利用」「高額療養費制度の簡易化」などメリットもあります。
紐付けしない方が「安全・安心」という誤解について
「マイナンバーカードに保険証紐付けするのは不安」「個人情報が漏れたら怖いから紐付けしない」という声もあります。ですが、整理して考えましょう。
個人情報漏えいリスクの現状
- 紐付け登録をしても、カードに膨大な医療/税/年金情報がそのまま保存されているわけではありません。
- 利用登録していない場合でも、従来と同じ保険診療は受けられ、「必ずしも紐付け=リスク」というわけでもありません。
- ただし、カード紛失・ICチップの破損・医療機関のシステムトラブルなど、注意すべき点はあります。
「紐付けしないことが安心」と言い切れない理由
- 紐付けしないと、将来制度が変わった際に旧保険証では対応できない可能性が高まります(例えば2026年12月2日以降の保険証制度見直し)
- 手続きの簡便さ・医療利用のスムーズさ・制度移行の観点で、紐付けをしておくメリットがあります。
- 「紐付けをしない=ずっと旧保険証を使える」という保証は制度上どんどん薄まっています。
2025年10月時点での制度最新ポイント💡
ここでは「何が変わったか」「今後こうなる」という点を、最新情報に基づいて整理します。
健康保険証とマイナ保険証の切替スケジュール
- 2024年12月2日から、従来の健康保険証の新規発行停止。
- 2026年12月2日以降、発行済みの従来保険証も使用できなくなる(または最長1年の経過措置あり)という案内が出ています。
「資格確認書」の運用
- 紐付けしていない方には、保険者から「資格確認書」が無償で交付され、保険診療を受ける際の代替手段となります。
- この交付は、申請不要で自動交付されるケースもあります(マイナンバーカードを未所有、あるいは利用登録していない方など)
同意・データ連携に関するポイント
- 紐付け登録とは別に、「過去の薬剤情報や健診データを医療機関と共有するか(同意)か」を選べる仕組みがあり、同意しない場合もマイナ保険証自体は使用可能です。
- ただし、同意していると「高額療養費制度の自動適用」「医療情報に基づく医療提供の質向上」などのメリットが受けられます。
医療機関の対応状況
- 全ての医療機関・薬局がマイナ保険証対応というわけではなく、対応が遅れている施設もあります。例えば「オンライン資格確認システム」の導入率が100%とはなっていません。
- 受診前に、利用する医療機関がマイナ保険証に対応しているかを確認しておくと安心です。
「ではどうすれば安心か?」紐付け手続きの流れとチェックリスト✅
ここでは「何をしておけばいいのか」「どこまで手続きすれば安心か」を、具体的にご説明します。
手続きの流れ
- マイナンバーカードを取得していない場合 → 申請・取得。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録を行う。
登録方法は:
・医療機関・薬局にある顔認証付きカードリーダーから登録。
・「マイナポータル」アプリや対応ATMから登録。 - 医療機関・薬局でカードを提示し、保険診療の手続きにカードを使用する。登録済みであれば以後スムーズに保険利用が可能。
✅チェックリスト(紐付け前に確認すべきこと)
- マイナンバーカードの有効期限(カード自体・電子証明書)を確認。電子証明書の有効期限が切れると保険証利用登録ができない場合があります。
- 加入している保険者(会社の健康保険、国民健康保険など)で紐付け登録が可能かどうか。
- よく利用する医療機関・薬局が「マイナ保険証対応」としているか事前に確認。対応していないと旧方式または資格確認書が必要になる可能性があります。
- 過去の薬剤情報・健診データ共有(同意)をするかどうか、自分の意向を確認。共有しない場合でも利用は可能ですが、メリットが一部受けられなくなります。
- 紐付けしない場合、資格確認書の存在・手続きについて理解しておく。特に保険者変更時など、保険資格の確認がスムーズでない可能性があるため。
Q&A
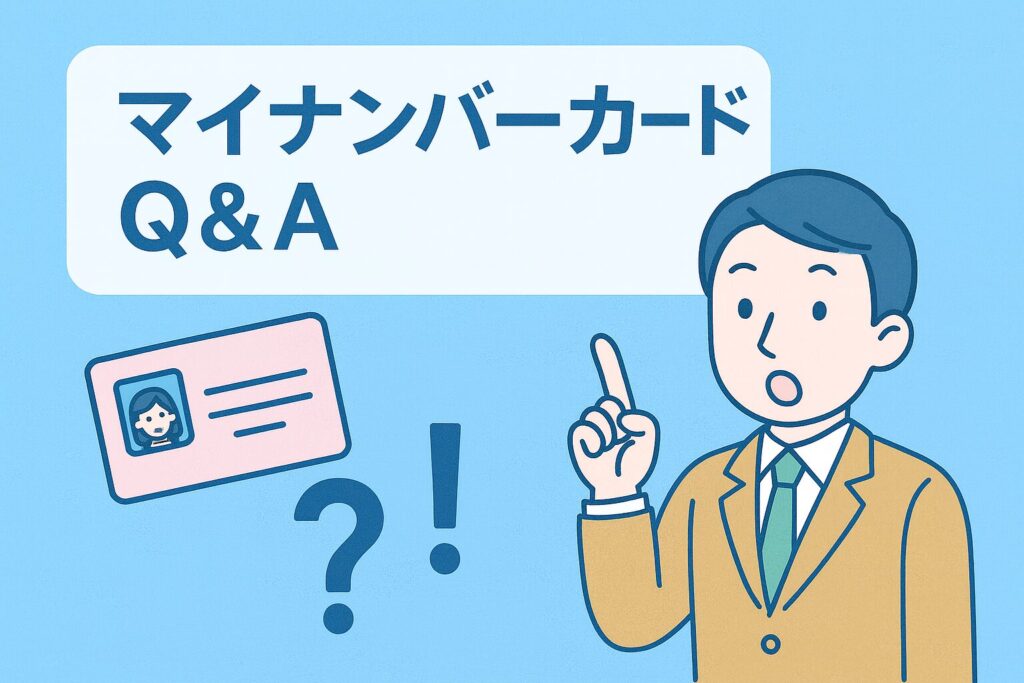
よくある疑問をまとめておきます。
Q1:紐付けをしないと、医療機関で受診できなくなりますか?
A:いいえ。カードを紐付けしていなくても、「資格確認書」が保険者から交付されていれば受診は可能です。
ただし、受付で手続きに時間がかかったり、カード提示による手続きの簡便さは享受できない可能性があります。
Q2:手続きには費用がかかりますか?
A:マイナンバーカード取得時の費用(交付手数料など)を除き、カードを保険証として使う登録そのものに追加の費用がかかるという情報は制度上出ていません。
また、「資格確認書」も保険者が無償で交付するケースがあります。
Q3:紐付けをしてしまった後で解除できますか?
A:はい、保険者に申請することで、カードの健康保険証利用登録を解除することが可能です。解除後、資格確認書の交付対象になる場合があります。
Q4:紐付けしないと高額療養費制度などが使えなくなりますか?
A:制度自体は利用可能ですが、「マイナ保険証を通じたオンライン資格確認+データ連携(同意)」という形での優遇措置(窓口負担の軽減等)があるため、紐付け・同意をしておいた方がメリットを享受しやすいです。
まとめ:紐付けを“しておいて安心”の理由
- 現時点では紐付けをしなくても保険診療自体を受けられますが、制度移行・手続きの簡便さ・将来的な安心という観点から、紐付けをしておくほうがメリットが大きいと言えます。
- 特に「転職・引越し・保険者変更のタイミング」や「急な受診時」のリスクを減らしたい方には、早めの手続きをおすすめします。
- 紐付けしていないことで即「大変なペナルティ」というわけではありませんが、制度変更の流れを考えると“手元の安心”のために動いておくのが賢明です。
- 不安に思う個人情報の扱いについても、カードには必要最低限の情報が登録されており、制度側は安全性対策を整えています。安心して手続きを検討してみてください。
今後、制度の細かな改変や運用上の変化が出る可能性もありますので、加入している保険者・お住まいの自治体の案内もチェックしながら進めていきましょう。