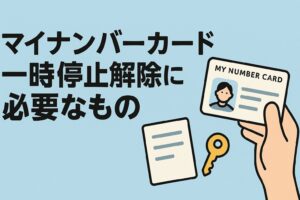新たにマイナンバーカードを申請しようとしている方は
「写真ってどこで撮ればいいの?」
「スマホで撮って大丈夫?」
「写真館や証明写真機とどう違うの?」
と疑問を持つのではないでしょうか?
――そんな疑問を持つ方に向けて、2025年10月時点の最新情報を踏まえて、「マイナンバーカード用の顔写真はどこで撮るべきか?」をわかりやすく解説します。
1.まずは「どんな写真を用意すれば良いか」?
写真の撮影場所を検討する前に、そもそもどんな写真がマイナンバーカード申請で必要なのかを押さえておきましょう。
✅ 写真の基本的な規格
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 撮影時期 | 最近6か月以内に撮影されたもの |
| サイズ | 縦4.5 cm × 横3.5 cm(ふちなし) |
| 背景・向き | 無背景(白や明るい単色)、帽子・サングラスなし、正面向き・顔の輪郭がはっきり |
| 表情・状態 | 普段通りの顔貌で、明るさ・ピント・影などがないこと |
| 裏面記入 | 写真の裏に氏名・生年月日を記入して貼付 |
✅ スマホ撮影も「可能」だけど注意が必要
公式サイトでも、スマートフォンで撮影した写真での申請は可能とされています。
ただし、暗い・影がある・正面でないといった規格外の理由で却下されるケースもあります。
スマホで撮る場合は、規格をきちんと満たしているか自己チェックすることが重要です。
2.どこで撮る?3つの主要な選択肢とそれぞれのポイント💡
「写真をどこで撮ればいいか?」という問いに対して、主に次の3つの選択肢があります。
A. スマートフォン(自宅・手軽に)
メリット
デメリット
おすすめポイント💡
- 背景は白や明るい色、影が出ないよう自然光やライトを使う。
- スマホを固定し、レンズを顔と平行に。
- ピント・明るさ・表情をチェックしてから申請。
B. 証明写真機(街中・コンビニ・駅など)
メリット
デメリット
おすすめポイント💡
- QRコード付き交付申請書を持参。
- 撮影後に確認画面で構図をチェック。
- 「データ送信」機能付きならその場で申請まで完了できる。
C. 写真スタジオ/写真館(確実重視)
メリット
デメリット
おすすめポイント💡
- 写真の仕上がりにこだわりたい人に最適。
- プロの調整により再提出リスクがほぼゼロ。
- 10年間使用する写真として安心。
3.どの方法を選ぶ?選択基準&おすすめ比較
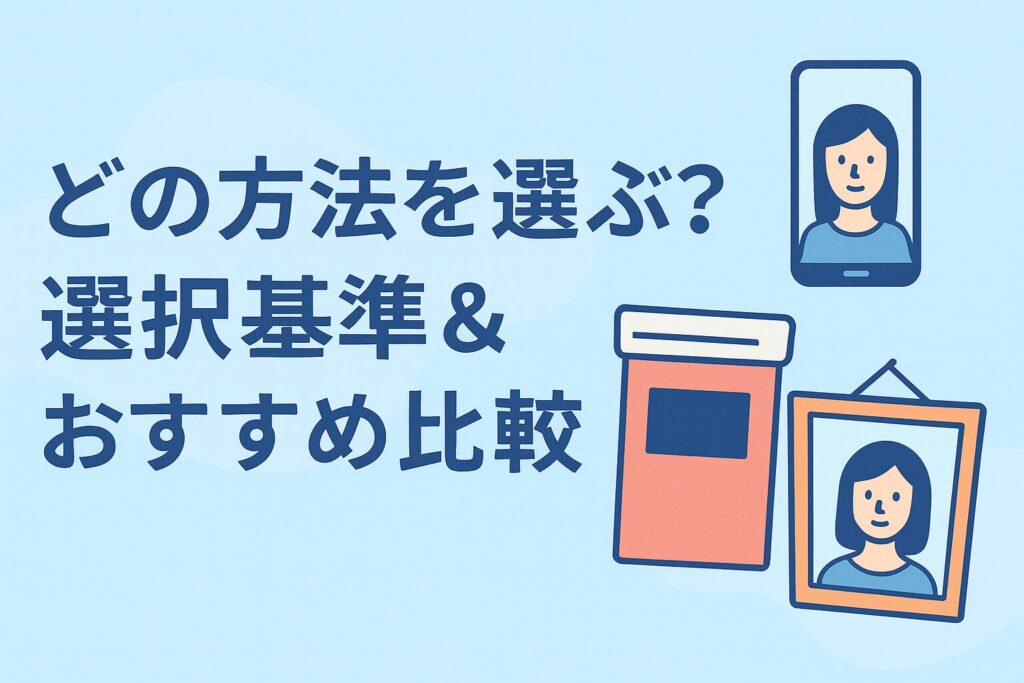
| 基準 | スマホ | 証明写真機 | 写真スタジオ |
|---|---|---|---|
| 費用 | ◎ 無料〜 | ○ 約800円〜1,000円 | △ 約2,000円〜5,000円 |
| 手軽さ | ◎ | ○ | △ |
| 写真品質 | △ | ○ | ◎ |
| 申請のしやすさ | ○(オンライン可) | ◎(その場で申請可) | ○(別途申請) |
| 再撮影リスク | 高め | 低い | ほぼなし |
4.自治体の無料撮影サービスもある
一部の自治体では、窓口で無料の顔写真撮影サービスを実施しています。
例)大阪府八尾市、栃木県宇都宮市など。
ただし、すべての市区町村で実施しているわけではなく、事前確認が必要です。
また、撮影データをもらえない場合もあるため、申請専用と考えておきましょう。
📌参考記事:八尾市ホームページ
📌参考記事:宇都宮市ホームページ
5.「写真が却下された」場合の原因と対策
| よくあるNG例 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 背景に影や柄がある | 光の当たり方が不均一 | 壁から離れて撮影・白背景推奨 |
| 顔が横向き・笑いすぎ | 規定外の表情・角度 | 正面・自然な表情 |
| 暗い・ピントがぼけている | 明るさ不足・手ブレ | ライト使用・三脚固定 |
| サイズや余白が違う | カード規格外 | 4.5×3.5cm・ふちなしを守る |
| 氏名記入なし | 裏面記入忘れ | 写真裏に氏名・生年月日記入 |
6.撮影から申請までの流れ
写真撮影の“どこで?”だけでなく、“どう申請するか?”の流れを整理すると安心です。
写真撮影から申請までの一般的なステップ
- 申請書(郵送・オンライン・窓口)を準備(交付申請書+QRコード付き/紙申請書)
- 写真撮影(スマホ/証明写真機/スタジオ/自治体窓口サービス)
- 写真データ添付または写真プリント貼付
- オンライン申請:スマホで撮影・データアップロード。
- 郵送申請:写真プリントを申請書に貼付して投函。
- 窓口申請:その場で撮影&手続き。
- 申請後、約1~2か月で「交付通知書」が届く(地域・申請数による)
- 通知を受け取ったら、市区町村窓口でカードを受け取る。写真はカードに印刷され、この顔写真がカード利用中10年(成人)/5年(未成年)使われます。
撮影場所ごとの流れ比較
| 撮影方法 | 準備するもの | 当日の流れ | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| スマホ | スマホ・交付申請書(QRコード) | 自宅等で撮影 → データアップロードまたはプリント貼付 | 撮影・アップロードが自分で要調整 |
| 証明写真機 | 交付申請書(QRコード)・お金(料金) | 機械でQRコード読み取り → 撮影 → 申請完了またはデータ取得 | 設置場所・混雑・撮影回数に注意 |
| 写真スタジオ | 予約(または店舗へ)・交付申請書 | プロ撮影 → データ・プリント取得 → 申請(オンライン/郵送) | コスト高・予約必要な場合あり |
| 自治体窓口撮影サービス | 本人確認書類・交付申請書 | 窓口に行って撮影 → 申請手続き | 実施していない自治体もあるので事前確認必須 |
7.2025年10月時点での「ここが新しい/注意したい」ポイント💡
2025年10月時点で押さえておきたい最新の動向や注意点を整理します。
- オンライン申請の普及により、スマホ撮影+データ申請の流れがさらに一般的になっています。
- 各自治体で「窓口での無料顔写真撮影サービス」が増えてきており、コスト・手間を抑えたい方には選択肢が広がっています。
- 写真規格や申請手続きの要件は変更が少ないものの、撮影機器・証明写真機の申請機能強化(例:機械から直接申請)などサービス面で利便性が上がっています。
- 「長期間(成人なら10年)写真が変えられない」ことを意識すべきです。写真にこだわれるタイミングで撮っておくのがおすすめ。
- 各市区町村によってサービス内容(無料撮影、有料、有無)が異なるため、お住まいの自治体の最新情報を必ず確認してください
8.よくある質問Q&A🔍
Q. スマホで撮って本当に大丈夫?
A. 可能です。ただし影・暗さ・ピント・背景などが不適切だと却下される可能性があります。
Q. スタジオ撮影のメリットは?
A. 品質・安心感が圧倒的。再撮影の心配がなく、長期使用に向いています。
Q. 役所で撮れるって本当?
A. 自治体によっては無料で撮影&申請代行してくれます。事前に市区町村のHPで確認を。
Q. 写真をあとから変更できる?
A. 基本的にはできません。再発行が必要です。初回で納得できる写真を用意しましょう。
9.まとめ:あなたに最適な撮影方法
「写真をどこで撮るか」は、それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、あなたの状況・目的・予算・時間をもとに選ぶことが大切です。以下の指針を参考にしてください。
- コストを最優先・簡単に済ませたい → スマホ撮影
- 手軽さと安心感のバランスを取りたい → 証明写真機
- 写真の仕上がりにこだわりたい・長期間使うので満足のいくものにしたい → 写真スタジオ
- 無料で撮影できる自治体サービスが利用可能なら → 窓口撮影サービスも検討
いずれの方法を選ぶにしても、写真の規格を満たしているか、撮影後セルフチェックをきちんと行うことが重要です。